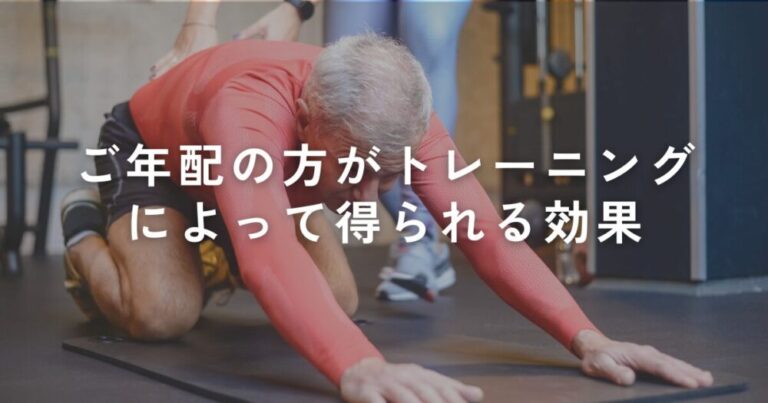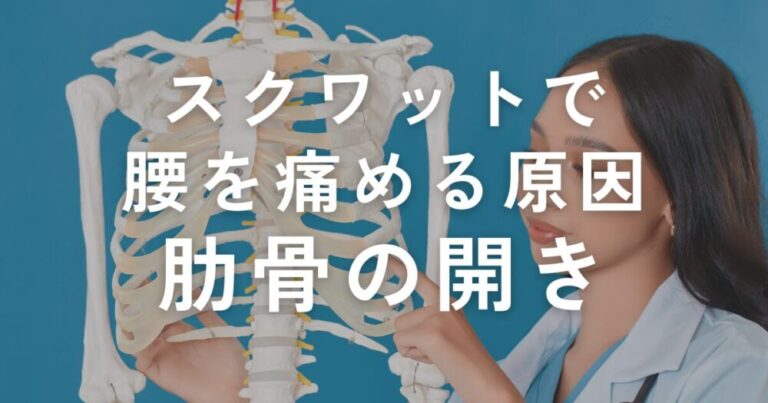「MoveConditioning」は日常のパフォーマンスを高めたい方はもちろん、身体の悩みの解決のためにコンディショニングにも力を入れている新丸子にあるパーソナルジムです。
こんにちは!トレーナーの高田です。
「トレーニング!」というと真っ先にイメージがつきやすいエクササイズの一つかもしれません。
私も基本的にトレーニング指導の中にほとんどプログラムに取り入れることが多いです。
もちろん、ご自身でトレーニングをされている方も多くの方がやっているエクササイズではないでしょうか。
そんなスクワットですが、日常生活の動きにも大きく関与することから多くの方に有益な効果を与えてくれるエクササイズになります。
なので私もとても重要視しています。
そんなわけで今回はスクワットの重要性について簡単にお伝えできればと思います。
- スクワットと日常生活のつながり
- スクワットでの評価ポイント
- まとめ
1.スクワットと日常生活のつながり

日常生活においては「歩く」、「立つ」、「座る」などといった動きを多く行ないます。
これらの動きに共通しているのが前後(矢状面)にかかるストレスです。
スクワットの動きを思い浮かべていただけると、「しゃがむ」「立ち上がる」といった前後の掛かるストレスをコントロールして行ないます。
その動きの中では「地面を押す」「上体を起こす(胸を張る)」といったことも含まれていますので立ち上がり動作や歩行などにも大きく関与します。
スクワットは日常生活に結びつき、適切に行なうことで普段の日常生活の動きの効率も上がり、楽に過ごしやすくなると同時に体への負担も軽減することに繋がります。
2.スクワットでの評価ポイント

スクワットのチェックポイントとしては大きく分けて以下の通りです。
・姿勢
上体は倒れずに起きているか
・膝関節、股関節、足関節の角度
それぞれの関節がバランスよく曲がっているか
・膝とつま先の向き
動作中、膝の向きおよび位置はどこにあるか
・重心の位置
足裏全体、かかと、つま先のどこで捉えているか
・力の向き
力の向きは真上に発揮されているか(鉛直方向)
・動作の安定
動きにブレがないか
・動作のスピード
スピードの調節ができているか
不適切なスクワットの場合、かえって体を痛めたり動きを不効率にさせてしまう恐れもあります。
問題点があれば、それらを改善して適切なスクワットを行うことを目指します。
3.まとめ
・日常生活においては「歩く」、「立つ」、「座る」などといった動きを多く行なう。
これらの動きに共通しているのが前後にかかるストレス。
・スクワットは「しゃがむ」「立ち上がる」といった前後の掛かるストレスをコントロールして行なう。
その動きの中では「地面を押す」「上体を起こす(胸を張る)」といったことも含まれるため、
日常生活における立ち上がり動作や歩行などにも大きく反映される。
・適切なスクワットができていれば日常生活の動きの効率も上がり、楽に過ごしやすくなると同時に体への負担も軽減する。
・スクワットの動作中の主なチェックポイント
姿勢
膝の関節と股関節の角度
膝とつま先の向き
重心の位置
力の向き
動作の安定
動作のスピード
そんなわけでスクワットは日常生活にも非常に有益な効果をもたらすことから、とても重要視しているエクササイズの一つです。
体に痛みが出るなどを感じる方は、一度専門家にご相談することをおすすめいたします。
そんなわけで何かご参考になれば幸いです。
それでは!
MoveConditioningの体験セッションのお申し込みはこちらからどうぞ↓

LINE公式アカウントでもご予約の申込みやお問い合わせなどが可能です!

健康や身体に関する情報やエクササイズなどをご紹介しています。
当スタジオのInstagramはこちらからどうぞ↓